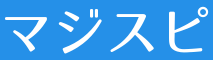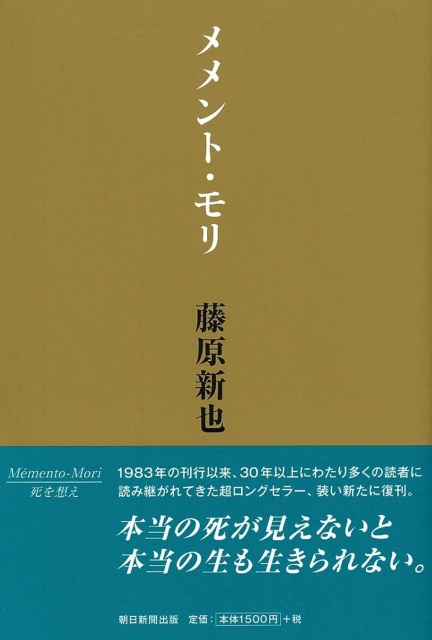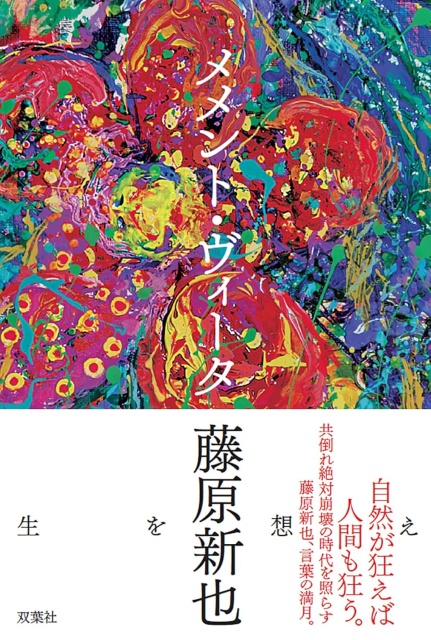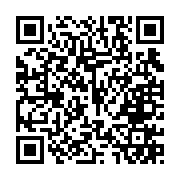※ウェブサイト『マジスピ』には音声の文字起こし(読みやすく加筆修正済)があります。
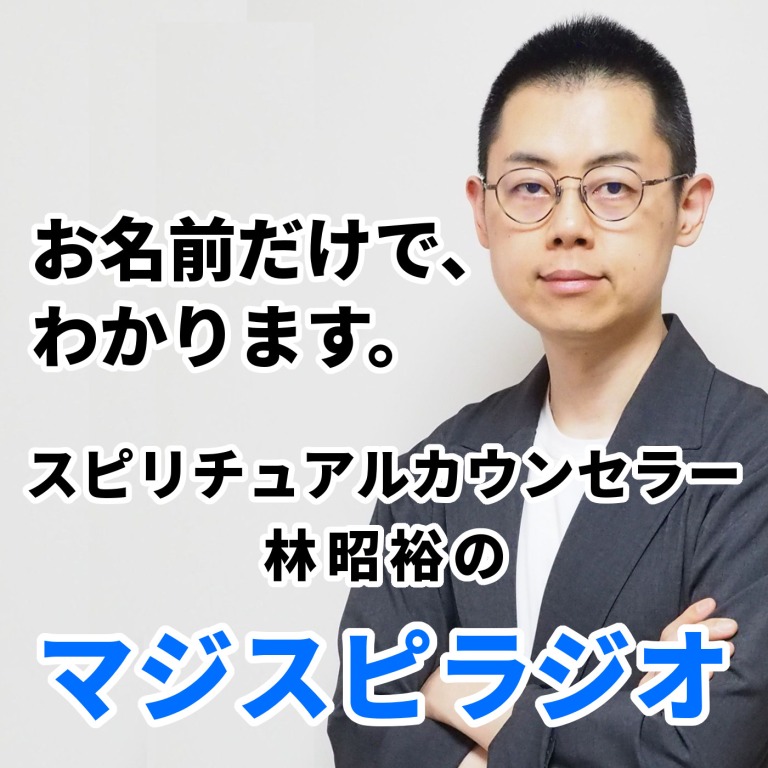
■今回は以下のブログを違う角度から語り直しました(https://prism-life.com/memento-mori/)
■YouTubeではメモ、資料、スライドなどを映していますが、音声プラットフォームの「ながら聞き」でも十分ご理解いただけると思います。
ウェブサイトでは最下部に音声プレーヤーがあります。倍速再生も可能ですし、YouTubeより通信量も少ないし、スマホを画面オフにしても聴けるので便利です。
■マジスピ・サブラジオ(stand.fmで配信中)
https://x.gd/o4EIt
■ご感想・ご質問は『アンケートフォーム』からどうぞ
https://x.gd/Mp7Lg
目次
『メメント・モリ(死を忘れるな)』の衝撃:現代に警鐘を鳴らす一冊
今回の文字起こしの要点
- 写真集『メメント・モリ』と『メメント・ヴィータ』を題材に、「死」と「生」の根源を考える。
- 死を見つめない大半のスピリチュアルは「お花畑」だと考えて間違いない。
- 「死を見つめること」は、宇宙の根源とつながる行為であり、魂の力を呼び覚ます鍵となる。
- 生命至上主義、生命礼賛、「生きることは素晴らしい」の時代に、「死を見つめて生きる」ことはスピリチュアルの実践となる。
今回は写真集『メメント・モリ』について取り上げます。
これはロングセラーの写真集なんですが、それは「本物の人生、運命を歩むには死を見つめる以外ない」という、その真実を突きつけてくるものです。
これは以前も話したことがありますけれども、大切なことなので繰り返し繰り返しこと語ることが大事という意味で、今回も話していきます。
この写真集、ご存知の方もいらっしゃると思います。
藤原信也さんという写真家の方の作品ですね。
私が初めて読んだのはもう20年以上前だと思いますが、非常に感銘を受けました。
【メメント・モリ】
今、YouTubeだとAmazonで画像が映っていると思います。
長く売れ続けているうちに表紙は何回か変わっています。
【メメント・モリ】(Memento Mori)というのはラテン語で、「死を忘れるな」「死を想え」という意味です。
昔、音楽でミスターチルドレン──もう誰でも知っているミスチルですが──の「花」という曲のサブタイトルが【メメント・モリ】でした。
花はそう遠くないうちに散ってゆく。それは我々もまた同じ。
この時期のミスチルは、だいぶダークな雰囲気が出ていましたね。
さて、写真集の帯には「本当の死が見えないと、本当の生も生きられない」と書かれています。
これはまさに、そのものズバリのメッセージ。
ちなみに、検索してみるとどうやら新刊の写真集が出ることがわかりました(ブログ投稿時点)。
2025年の5月21日、もうすぐですね。
【メメント・ヴィータ】っていうタイトルです。
この配信のタイミングで取り上げられたのは、非常に良いタイミングでしたね。
ベストセラー【メメント・モリ】から40年余りを経て、【メメント・ヴィータ】が発表された。
「ヴィータ」(Vita)はラテン語で「生きる」「命」などを意味します。
つまり、【メメント・ヴィータ】は「生を想え」という意味になるわけですね。
今度はそう来たか・・・ぜひ読んでみたいと思いました。
『メメント・モリ』には、今のメディアでは見られないような写真が収録されています。
ネタバレになるので具体的には言いませんが、テレビはもちろん、インターネットメディアやYouTubeでも映らないような、生きとし生けるもののリアルな姿がそこにあります。
そして藤原さんの言葉──詩のような言葉──も非常に印象的です。
もしご興味があれば、ぜひ一度手に取って読んでみられるといいと思います。
あるいはお近くの図書館にも、けっこう置かれているのではないでしょうか。
私の近くの図書館にもありました。
今回の配信をご覧いただいて興味が出たら、ぜひどうぞ。
本来サクッと読めるような内容ではありませんが、写真集ですのでそんなに時間はかかりません。
今回が第305回か306回目の配信だと思いますが、第233回、つまり1年以上前に
「死生観の欠けたスピリチュアルは寝言かお花畑である」
というテーマで話をしました。
この考えは、今もまったくぶれていません。
私はマジスピ(真のスピリチュアル)に対し、よく「普通のスピリチュアル」と言います。
この普通のスピリチュアルでは「死生観」、つまり死ぬ・生きるというテーマをほとんど扱いません。
あの世がどうの、生まれ変わりがどうの、ソウルメイトがどうのといった「あの世的」な話はしますが、現実の問題として最も根源的な「死」について触れることはほとんどありません。
以前から言っているように、「生」──つまり【メメント・ヴィータ】ばかりを語るんですね。
ただ、この「ヴィータ」というラテン語の響きは美しいものがあります。
ラテン語は古い言語なので、「言霊」として優れた波動を持っています。
私たち日本人もまた、言霊を重んじる文化を持っていて、日本語には古来の言葉が多く残っている。
いつも冒頭で「お名前だけでわかります」と言っているのは、言葉の波動を感じ取っているのです。
そこで「ヴィータ」というラテン語の波動を感じてみると、非常に素晴らしいものを感じます。
地上は実は「死の世界」、霊界こそ「輝ける世界」
この「生」とは対照的に、「死」は忌み嫌われる傾向にあります。
私は職業柄、土地や物件の鑑定で波動をよく拝見するのですが、部屋の番号に「4」はないですよね。
204号室や405号室など、4は忌み嫌われる数字です。
けれど、本当は「死」こそ根源なんですよ。
死の世界は暗い、死んだら闇、お先真っ暗──なんて普通は言いますけれども、本当はそうではない。
この世の時間というのは、本当に一瞬。
ある意味では「偶然の事故」のようなものですね。
確か心理学者の河合隼雄先生も「生まれるっちゅうことは、事故みたいなもんですわ」と、どこかでおっしゃっていた記憶があります。
死の世界こそが本体、本当の世界なのです。
前に紹介したシルバーバーチも「霊界こそ本当の世界であり、あちらから見ればこの地上こそ死の世界であり、影の世界なのです」と述べています。
「死ぬこと」を「往生」と言いますよね。
「往生」とは、あの世に"往"き、そしてあの世で"生"まれるという意味。
つまり、この世での「死」は、あの世での「誕生」なのです。
そして、あの世こそが本体、本当の世界であるために、実は死は恐ろしくない。
それが本当の姿だということです。
これはスピリチュアルをちゃんと学んでいる人であれば、頭では分かっていると思います。
私も10代からこういった「死」について時々考えてきました。
お葬式でよく唱えられる一節に、こうありますね。
「朝には紅顔ありて、夕べには白骨となる」
たしか浄土系の宗派だったと思いますが、この言葉がよく使われます。
朝は紅顔、つまり若くて生き生きとした表情でも、事故や不慮の事態があれば、夕方には白骨になっている。
それがこの世の「無常」だということですね。
お葬式はもちろん、故人を弔う儀式ですが、お坊さんが唱えるお経は、むしろ私たち生きている側へのメッセージではないでしょうか。
お経には供養の力があります。
お経を唱えることによって、その波動が亡くなった方に伝わる──本当に力のある僧侶が唱えれば、伝わるものがあります。
もっとも、修行不足の僧侶も多く、口先だけで何の力もないお経もあるのは確かですが……。
それはさておき、死を忌み嫌う限り、本当の意味での生の充実は訪れません。
なぜ私たちは死を怖れるのでしょうか?
おそらく「肉体の痛み」ではないでしょうか。
つまり死そのものというより、「死ぬときに痛い」「苦しいのではないか」と感じるのだと思います。
ただし、医師の言葉や文献などを見ると、意外にも死の直前というのは痛みがあまりない。
精神的に安定している場合、なおさらです。
脳科学的にも、死の間際には天然の鎮痛剤のような物質が分泌されるとも言われています。
悔いなく生きた方の死に顔というのは、非常に安らかです。
私も仕事柄、亡くなる直前の方と「死んだらどうなるのか」「どこへ行くのか」といった対話を何度かしてきました。
そうやって死を受け入れた方は、本当に安らかに旅立っていかれます。
まさにそれが「往生」なのです。
さて、そういった話をしていると、数年前の感染症騒動を思い出します。
あれで馬鹿騒ぎをしていた当時(2020年3月)、私は一本の動画を出しました。
そのタイトルは「コロナ騒動に関して思うこと」。
サムネイルには「コロナでなくとも人は死ぬ」という文言を書きました。
ところで、この【メメント・モリ】という言葉は、実は中世ヨーロッパで起こったペスト(黒死病)の時代に盛んに使われたものでした。
アルベール・カミュの小説『ペスト』も、当時かなり売れていましたね。
この言葉は、性・生が刹那的・享楽的になっていた中世末期のヨーロッパで宗教用語として使われていたのです。
信じられるものがわからなくなった時代──死者が多すぎて、信仰にすがるしかなかった。
3人に1人が亡くなってしまうような、本物のパンデミックでした。
その時代にはまだキリスト教の価値観が色濃く残っており、宗教もまだ息づいていた。
つまり「神がまだ死んでいなかった時代」だったんですね。
だから根本である死を見つめようとする気概が、人々の中にまだまだ残っていた。
ところが、ペストを経た後のヨーロッパでは、次第にヒューマニズムが台頭し、人間存在を称える一方で神を忘れていく時代に入ります。
そして今、私たちは「神が死んだ時代」に生きている。
物質主義が全盛のこの時代、私たちは自ら「神を殺してしまった」わけです。
そんな中で、私はこの配信日から約5年前、「コロナでなくても人は死ぬ」と言ったのです。
感染症であれ、ガンであれ、原因が何であれ、人は必ず死ぬ。
だからこそ、それを見つめなければならない。
小さな感染症ごときで何をそんなに騒いでいるのか──いつか必ず人は死ぬのに。
ただ、当時はこういったことを語る人は少なかったですね。
多くの人が「怖い」「感染が怖い」と恐れていました。
感染したら、周囲から隔離され、まるで村八分にされるってね。
つまり、肉体の快・不快、そこに意識が集中していた。
これは「生命至上主義」と言います。
「この肉体の命こそがもっとも価値がある」とする考え方ですね。
だからこそ、「命を守ろう」「命を守るためにアレを打ちましょう」と、例の“腕に打つ謎の薬剤”を推奨した。
(当時さんさん煽った専門家はいま、手のひら返しで「アレに感染予防効果はあまりなかったです」と平気で言ってますが)
では、それからどうなったか?
コロナ前とコロナ後──社会のシステムが大きく変わってしまいました。
けれど、そんな“未曾有の危機”の中で、「死」をきちんと見つめていた人がどれだけいたのでしょうか?
さっきも言った通り、スピリチュアルの情報をいろいろ見てきましたが、本当に大切な死について語っている人は、正直あまり知りません。
もちろん私自身もすべてをチェックしているわけではありませんが、やはり中世のヨーロッパに比べたら、それは失われてしまった。
だからこそ、私たちの魂も全体として堕落してしまっているのだと思います。
その中で、私も含め「真のスピリチュアル(マジスピ)」を探求したいと思っている人たちは、やはり基本の構えとして「常に死を見つめる」ことが大切だと感じます。
それをもう少し広く言えば、「ご先祖を見つめる」こともまた「死を見つめる」ことにつながります。
魂を遡っていけば、ご先祖という存在があり、その「死」の上に今の自分の束の間の「生」があるのです。
昔の中国の言葉に「我は父母の遺体なり」という表現があります。
つまり、自分という存在は、両親がこの世に残したものであり、先祖の「死」の上に成り立っているということです。
「死を見つめること」は、宇宙の根源と向き合うこと
こうして死を見つめていく先に、「命のつながり」や「なぜ今ここに自分が存在しているのか」という問いに自然と向き合うことになる。
それが日本人が実践できる一つの【メメント・モリ】であり、やがて【メメント・ヴィータ】にも通じるわけです。
スピリチュアルではよく「宇宙」という言葉が使われますね。
私たちは「宇宙の根源」から生み出され、束の間の「生」を生きて、やがて宇宙に還っていく。
「死ぬ前の世界」と「死んだ後の世界」は、どちらも無限の創造力を持つ宇宙に通じているわけです。
だからこそ、「死を見つめる」という行為は、実は宇宙の根源に触れることと同じなのです。
それは「死」が数年後、あるいは数十年後の遠い出来事ではなく、「今ここ」に存在しているものだと気づくこと。
「今ここ」に「生」があるということは、同時に「死」もまた足元にあるということ。
第233回でも述べましたが、サムネイルにも書いたように「死生観を定めると、魂の力、天命の力が発動する」──これはまさに、今回のテーマと重なります。
なぜか?
「死を見つめる」ことは「宇宙を見つめる」ことだからです。
宇宙は無限のエネルギーであり、だからこそ魂の力が発動する。
日々を惰性で生きるよりは、よほど意味のある生き方に近づけるでしょう。
だから、「死が怖い」「恐ろしい」という感覚──これは肉体を本位とした価値観から来ているわけですが──その奥にある「大いなる命の世界」を見つめることが大切なのです。
ただし、これは簡単ではありません。
「死を見つめる」ことには慣れるまでは、いや、慣れてもなお苦しさがあります。
やっぱり怖い、嫌だ、面倒くさい──そう思うのは自然なことです。
肉体という自己保存本能を持つ限り、死を見つめることは苦痛に決まっています。
実際、死を思ったところで、直接的な利益があるわけではない。
だからこそ、これはもう「心がけ」しかありません。
私は毎日、死を思い、ご先祖や、先の戦争で命を捧げてくださった英霊の方々のことを想うようにしています。
人間は忘れやすいものです。
私も未熟な人間なので、何度も何度も思い返す機会を持たねばなりません。
今この記事を読んで「なるほど、やっぱり死を思うのは大事だな」と思ってくださっても、あなたはきっと数日で忘れてしまうでしょう。
それはあなただけではない、私もそうです。
だから、毎日「生死の根源」を思い出す工夫が必要です。
【メメント・モリ】は、宇宙エネルギーに触れることであり、真剣でなければ向き合えないテーマです。
私自身もこうして配信で話しながら、ブログを書きながら、しょっちゅう自分自身に言い聞かせています。
なぜ「死」を忘れたスピリチュアルは危ういのか?
そうやって、少しずつ「死を見つめる」ことに慣れていく。
いや、決して慣れることはないけれども、見つめる機会は増えていく。
それが真のスピリチュアル──マジスピ──の「必須科目」です。
逆に普通のスピリチュアルに触れれば触れるほど、逆に「死」は忘れ去られていく。
その結果、魂はだんだんと腑抜けになり、オーラ(波動)も重くなり、濁っていきます。
皮肉なことですね。
オーラが黒くなる、重たくなるというのは分かりやすいですが、そうでなければ「霧がかったような」「ぼんやりした」感じになります。
ただ生きてるから生きてるような、ただ時間だけがスーッと流れていくような、そんな毎日になります。
そして、生きている間、特に生命が燃え立つこともなく、一つの人生が煙のように消え果てていく。
それが嫌であれば、一日のどこかで、真剣な気持ちで「死を思う」時間を持つといい。
この『メメント・モリ』の写真集には、正直きつい写真もあります。
けれども、パッと目を通すだけでも良い刺激になります。
ですので、手元に置いておくのも良いかもしれません。
そしてその上で『メメント・ヴィータ』──生を思え──という新刊も出ています。
まさか今回の配信の数日後に40年ぶりの新作が出るなんて、本当に絶妙なタイミングでしたね。
ともかく、本当のスピリチュアルとは、まさにこの両方(死・生)を見つめることなのです。
他のことは、死さえ見つめていれば、なんとかなる。
私もこの仕事をして10年以上になります。
そうすると、悩みのご相談以外に、スピリチュアル系の仕事や、カウンセリング、セラピーなどの道に進みたい方のビジネス相談を受けることもあります。
大半の方は、やはり踏み出すのが怖いのです。
うまくいくか分からない、失敗したらどうしよう……。
その恐れを完全に払拭する安易なテクニックはありません。
けれど「死を見つめる」こと──それは恐れの根源に向き合うことです。
怖れを超えて一歩を踏み出したければ、勇気を出して怖れそのものの中に入っていくしかありません。
どうせ泣いても笑っても人は死ぬのだから、合理的に考えても、死は早く見つめた方がお得ですよ。
そうすれば、他の怖れも乗り越えられるようになると、私は思っています。
はい、今回もずいぶん長くなりましたので、このあたりで終わりにしたいと思います。
今回は【メメント・モリ】──死を忘れるな──という写真集を取り上げて、「死を見つめないスピリチュアルは寝言である」という根本的なテーマをお話しました。
少しでもご参考になれば幸いです。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
改めて、今回の文字起こしの要点
- 写真集『メメント・モリ』と『メメント・ヴィータ』を題材に、「死」と「生」の根源を考える。
- 死を見つめない大半のスピリチュアルは「お花畑」だと考えて間違いない。
- 「死を見つめること」は、宇宙の根源とつながる行為であり、魂の力を呼び覚ます鍵となる。
- 生命至上主義、生命礼賛、「生きることは素晴らしい」の時代に、「死を見つめて生きる」ことはスピリチュアルの実践となる。
なお、YouTube(Podcast)は今回の文字起こし編集でカットした部分もあります。
なのでこちらも聞いていただけると、より理解が深まります。
※この下に「音声プレーヤー」があります。倍速再生も可能ですし、YouTubeより通信量も少ないし、スマホを画面オフにしても聴けるので便利です。